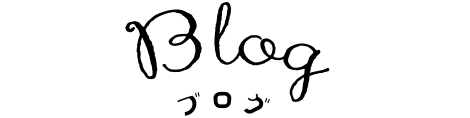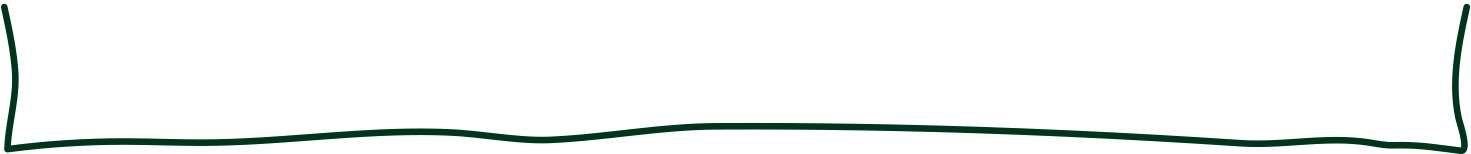ごはん好きの私ですが、晩酌をするようになってから、夕食のごはんは、食べなくなって久しいです。そんな昨今ですが、穀物を食べないことを見直さなくては!という、大妻女子大学家政学部食物学科教授 青江誠一郎氏の記事をみつけたので、ご紹介します。
1 日本人の食事摂取基準とは
2 食物繊維の目標値
3 もっと穀物を食べよう
1 日本人の食事摂取基準とは
今年は、厚生労働省が5年ごとに改定している「日本人の食事摂取基準」2025年版が出ました。これは、健康な個人、集団を対象として、国民の健康の保持・増進、生活習慣病の予防のためにエネルギーや栄養素の摂取量等の基準を示すものです。栄養素の指標として、推定平均必要量、推奨量、耐容上限量、目標量などがあり、私たちの身近なところで、学校給食や施設・病院の給食メニューなど、栄養士さんが作る献立の基礎として、今までもずっと活用されてきています。
2 食物繊維の目標値の引き上げ
さて、日本人の食事摂取基準の目標値の中で、今回引き上げられたのは、食物繊維の目標量です。例えば、30~64歳の男性は1日21g以上だったのが22g以上に、65~74歳の男性は20g以上だったのが21g以上とされました。65~74歳の女性も17g以上から18g以上になりました
ちなみに、WHO(世界保健機関)の推奨量はもっと多く、「1日当たり25~29gの食物繊維の摂取が、さまざまな生活習慣病のリスク低下に寄与する」ことから、1日25g以上を推奨しています。
「食物繊維を1日14g以下しか摂取していない人たちに比べて、25g以上とった人たちは明らかに死亡リスクが低下したという報告もあります。この研究では30g以上とっても問題ないことが分かったので、少なくとも25g以上とったほうがよいだろうと考えられるわけです」と、青江誠一郎氏は説明しています。
70年前の1955年には、日本人は1日当たり平均22.5gの食物繊維をとっていたといいます。多くの人が現在の目標量をクリアしていたことになります。
そんなに下がってるかしら。食物繊維って、サラダや副菜の野菜など、私も毎食摂ってるのに・・、と思ったら、これはそうではなかったのですね。
3 もっと穀物を食べよう
食物繊維というと野菜のイメージが強いですが、実は1955年の日本人は食物繊維の44%を穀類からとっていたのです。
1955年には22.5gとっていた食物繊維が、2018年には15gになりました。何が一番減ったかというと穀物です。炭水化物を減らし、ご飯を食べなくなった結果、70年前は食物繊維の44%を穀物からとっていたのに、2018年には穀物の割合が20%と半減してしまったのです。穀物の中でも、玄米や大麦のような精製していない全粒穀物は多くの食物繊維を含んでいるので、そうした穀物の健康への寄与は大きいといいます。
食物繊維の中でも、発酵性食物繊維は穀物に多く含まれています。もち麦や押麦を白米に混ぜて食べると、非常に多くの発酵性食物繊維が無理なくとれます。穀物以外では、大豆やバナナに多く含まれています。ゴボウなどの根菜類を除いて、通常の野菜にはほとんど発酵性食物繊維は含まれていません。
最後に
子供のころ、縦線の入った押麦を食べたことがあります。今は価格高騰している米に、かさ増しのためのもち麦、大麦などを入れている家庭も増えているといいます。食物繊維をより多く食べることで、結果的には健康にはよさそうですね。
食物繊維の目標量はどう変わった? 食事摂取基準の改訂で (3ページ目):トピックス:日経Gooday(グッデイ)
=プロフィール=
プラン行政書士事務所 代表行政書士 中西浩子
日本で暮らしたい、農業をはじめたい
さまざまな思いを全力でサポートします。